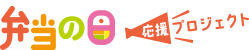presented by OVO [オーヴォ]話題の情報を発信するサイト
何年生まれか、どこの国か、にかかわらず、多くの女性がこの作品の一場面に自分を重ね、嗚咽(おえつ)する。ありふれた日常生活の一コマでありながら、優しい言葉でありながら、その向こう側にある目を背けたくなるほどの無理解が胸に重くのしかかる。「女性たちの絶望が詰まった本」(松田青子)とも形容される韓国のベストセラー小説を映画化した『82年生まれ、キム・ジヨン』が公開された。誰かの妻であり、母である以外の「自分」を失い苦しむ女性たちの孤独を、静かに、しかし確実に告発する作品だ。
原作は、2016年に刊行されたチョ・ナムジュの同名小説。タイトルの通り、1982年に生まれたキム・ジヨンという女性の生い立ち、結婚、出産、育児の日々を描いたもの。色濃く残る家父長制と職場での性差別に加え、子連れに冷たい社会や婚家と嫁の関係など、社会に織り込まれた不可視な網に絡めとられ、キム・ジヨンは精神に異常を来していく。
人気俳優コン・ユが演じるジヨンの夫、デヒョンは、とても優しいし、妻を理解しようとする真面目な夫だ。だからこそ、逆説的だがそこに潜む無理解が浮き彫りになる。子供の頃から“女の子らしさ”を求められ、高等教育を受けて手にしたキャリアを出産で投げうち、おむつを替え、夫の実家で台所に入り、ベビーカーを押して公園に行けば、「夫の稼ぎでのんびりできていいよな」とささやかれるジヨン。その全てを黙って引き受けてきた彼女の長い時間を共有した観客は、デヒョンの優しさに底の浅さを見てしまうのだ。母親だけでなく父親の子供でもあるのに、育休を取るのは「君のため」なのか、育児は「手伝う」ものなのか、育児のために仕事を辞め家にいることを「休息」と呼ぶ無神経さはどこからくるのか、と。どんなに苦しみを訴えても、場当たり的な優しさで素通りしていくように見える男性たちの滑稽な反応は、原作小説の最後に、ジヨンを診ていた男性精神科医が結局は何も理解していなかったのだと分かった時の読み手の衝撃を、違うやり方で再現しているように見える。
先に本を読んだなら、映画には多少救いを感じるかもしれない。ジヨンを診る精神科医は原作と異なり女性であり、自己嫌悪に陥るジヨンを励ます短い言葉に安堵する。落涙するのは、ジヨンの母親が怒りを爆発させる場面。この作品の醍醐味は、この母親の真意を理解できるか、劇場を後にした男性と女性が話し合うところから始まるのかもしれない。
text by coco.g